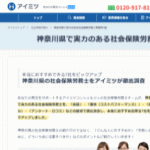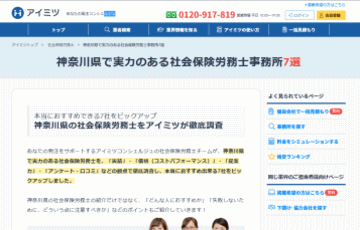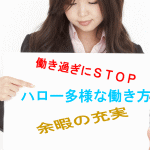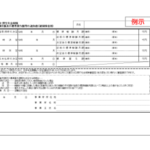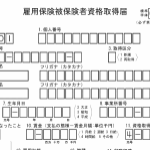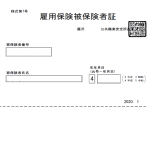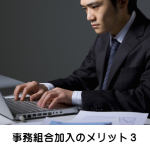最近の、テレビだったかネットの記事だったか次のようなものを見ました。コロナで小学校や保育園が休園になり「お母さんが会社を休まなくてはならなくなった」このような場合に対応して「小学校休業等対応助成金」という制度が設けられている
社会保険労務士
小さな会社に社労士は必要ですか?
小さな会社を設立しようと考えています。(社員2名アルバイト2名)社労士は必要でしょうか?
という問いに対するyahoo知恵袋の答えがこれです。いずれも一般の方(労務担当者?)とお見受けします。
社労士比較サイト「アイミツ」さんに掲載されました。
昨日当サイトの被リンクをチェックしていたところ「アイミツ」さんからリンクが・・
これは何かな?
と思ってアイミツさんをみているとなんと
「神奈川県の社会保険労務士」に掲載されていました。
ありがとうございます。
アイミツさんのサイトへ行く↓の画像をクリック
アイミツさんが意外とまめにチェックしてるのでビックリ。
できれば横浜市の方にも掲載お願いします。
check0%
働き方改革と社労士~その1~
働き方改革と中小企業
中小企業の経営者にとって働き方改革は、結構頭の痛い問題となっています。長時間労働の上限時間規制や有給休暇の取得義務、同一労働同一賃金、中小企業への時間外労働の割増賃金率猶予措置の廃止等々。
これまで法で定める労働条件を満たす労務管理ができていなかった企業にとっては、大きな問題担っています。
働き方改革は、単純に労働時間を短くしたり、有給休暇を取得させたりすればいいというものでは無く、人口減少社会において、労働生産性を高めることにより企業の業績向上、ひいては国としての競争力を向上させることを目標としています。その理念は賛同しているけれども、中小企業ではなかなか取り組めていない現状があります。
取り組めていない理由は、「人員に余裕がない」「何に取り組んでよいか分からない」「効果が分からない」などとなっています。
中小企業では、元々が長時間労働(変形労働時間制などを利用して週40時間労働でない企業はざらにある)であるのに加えて、納期に間に合わせるための残業は日常茶飯事、有休を取るなどはもってのほか、的な会社も多数存在しています。つまり、適切な労務管理に取り組む余裕がなく、ノウハウも持ち合わせていないのです。
さらに、人手不足が働き方改革を阻害する要因になっています。日本銀行による「全国企業短期経済観測調査」では、人手不足は全業種・全規模で過去最悪のレベルになっています。
人手不足だから働き方を改善しなければならないけれども、一方、人手不足なので働き方改善に手が回らない。この二律背反した問題に取り組まなければいけない。「労働力の確保と生産性の向上をワンセットにして対策を打っていかなければならない」のです。
しかし、繰り返しますが「働き方改革は残業を減らしたり有給休暇の取得率を上げればよいという単純な対応で済むものではなありません。」残業を減らすための作業効率化を行わず、作業を所定時間で終わらせることだけを強制したりすれば、従業員は疲弊するだけで働き方改革のメリットをまったく享受できず、共感も得られないでしょう。中小企業の働き方改革では従業員のモチベーションを低下させること無く事を進める必要があります。
働き方改革の実践には、ある決まったパターンはありません。
まず現状を分析し目標となるターゲットを定める。そこはみんな一緒ですが、実現する方策は会社によって異なるのです。『うちも働き方改革をやる』とだけ宣言しても、理念先行ではけっしてうまくいかないでしょう。
具体的には『残業は当たり前』に狙いを定めて集中した改善策を探り、結果的に労働生産性向上を目指す取り組みや。
「就業規則をきちんと見直して現在の法に適合したものにするだけで、高い改革効果を得られている」場合もあります。
「今回改正の対象となっている残業時間や割増賃金率、休暇制度などについて、きちんと定めた就業規則を作り実践すれば、それだけで働き方が変わる。その上で改善しなければならない事項が浮かび上がってくればそこを改善していく」そんな取り組みもあります。
社労士はさまざまな業種・業態、規模の経営現場に入り、そこで得た豊富な現場経験を基に、一社一社の実情に応じたきめ細かなアドバイスをすることができる。それは、経営者に「うちでもできる」という自信を与え、一歩を踏み出す後押しにもなっている。
専門家と相談相手の両面を併せ持った社労士は、経営者とそこで働く従業員のパートナーとして「人を大切にする企業」づ
くりを支援し、生き生きと働ける職場づくりをお手伝いしています。
社会保険労務士会が運営する働き方改革支援センターのご案内
社会保険労務士会が運営する「働き方改革推進支援センター」
「働き方改革推進支援センター」の主な支援内容(事業主対象)
長時間労働の是正
同一労働同一賃金等の非正規雇用労働者の待遇改善
生産性向上による賃金引上げ
人手不足の解消に向けた雇用管理改善
以下のようなお悩みはございませんか?
36協定について詳しく知りたい
非正規の方の待遇をよくしたい
賃金引上げに活用できる国の支援制度を知りたい
人手不足に対応するため、どのようにしたらよいか教えてほしい
助成金を利用したいが利用できる助成金が分からない
など
就業規則の作成方法、賃金規定の見直しなどを含めたアドバイスを行います。
具体的には、以下の支援を実施していますので、お気軽にご利用ください
個別相談支援
・窓口相談、電話、メールによる一般的な相談の受付
・企業へ直接訪問し、事業主の方が抱える様々な課題について親身に対応
・商工会議所・商工会・中小企業団体中央会等と連携し、より身近な場所での出張相談会の実施労務管理セミナー
・「時間外上限規制」、「同一労働同一賃金ガイドライン案」への取組みの周知、36協定の締結や就業規則作成に当たっての手続方法、その手法に合わせた労働関係助成金の活用等について、セミナーを開催
サポート体制
・社会保険労務士が、実際に支援を行った事例を紹介
サポート事例
支援センターをのぞいてみよう
社労士のできること
社労士に依頼しようとする方へ
「社労士にどんなことをしてもらえるのかわからない??」という事業主の皆さんの話をよく聞くので、社労士に依頼できるのはどんなことがあるのかお知らせできればと思います。ホリエモンさんに言わせれば「社労士なんていらないんじゃあナイ。就業規則なんて一部を除いてコピペでいいじゃん」だそうですが・・・(ホリエモンブログはここをクリック)
社会保険労務士(社労士)とはヒトに関する専門家
まず、社会保険労務士は、「社労士」やちょっと古い方々には「労務士」などと呼ばれる。わたしもフルネームで社会保険労務士と呼ばれることはまず無い。社労士の○○先生と呼ばれることが多い。方や、社労士の先生は自己紹介で「社会保険労務士の○○です。」という方が多いのはおもしろい。国家資格所持者であるというプライドであろうか。
社労士とは、労働・社会保険諸法令に基づく各種書類の作成代行や届出等を行ない、また会社を経営していく上で労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う国家資格を持った専門家である。言い換えれば「ヒトに関する業務」についてアドバイスをしたり実務サポートをする専門家といえる。世の中の社長さんの中には「営業は得意だが、管理業務は苦手」なかたも多くいらっしゃる。優秀な番頭さんがいれば事は足りるのだがそうで無い場合は、外部の専門家を頼るのも一つの方策である。
社会保険労務士に依頼できる仕事は、大きくわけて2種類ある。すなわち、「ヒトに関する手続きなどの事務の外注(アウトソーシング)」と「ヒトに関するコンサルティング」である。社会保険労務士の世界では前者を1,2号業務、後者を3号業務といっている。
社労士にヒトに関する業務を外注(アウトソーシング)する
ヒトに関する業務を外注(アウトソーシング)するとは、労働保険・社会保険に関する手続き、給与計算などを依頼することをいう。
- 社労士に依頼できる主な業務
- 社員の入社・退職時に雇用保険や健康保険・厚生年金の資格取得や喪失の手続き
- 業務上の負傷疾病・通勤途上の負傷疾病などの労働災害(労災)が発生したときの届出
- 社員に扶養家族が増減する場合(結婚・出産・離婚・死亡など)の健康保険の変更手続き業務
- 社員の住所や姓名が変更された時の雇用保険・健康保険などの変更手続き業務
- 会社が移転したり、支店や拠点が増減した場合の労働・社会保険上の手続き
- 社員の毎月の給与計算や勤怠管理業務
- 労働保険料の1年間分の保険料を計算して申告する業務(年度更新業務)
- 年一回、社員一人ひとり個別の社会保険料を計算して申告する業務(算定基礎届)
- 健康保険関係の給付(出産一時金・傷病手当金)手続き
-
社労士への業務アウトソーシングのニーズ
では、社労士に業務をアウトソーシングをするのはどんな場合なのでしょうか。あなたの会社がここに当てはまる場合は要検討です。
「ヒトに関する業務」を行う専門スタッフを置く余裕がない会社
社長自らが人事・労務関連の業務をおこなっていて、本来の仕事に支障をきたしているような会社が、どうしようもなくなって社労士に仕事を依頼する場合。
これは比較的起業した当初から多いです。確かに社長が行えば費用はかかりませんが、結構役所での待ち時間は馬鹿になりません。また、不慣れなため間違いも多く、最悪の場合、手続き漏れが発生している場合が多々あります。ひどい場合では半年ぐらい放置されてる場合もある。手続き漏れは、従業員にとって不利益になるし、行政官庁の立ち入りなどでは厳しく指摘される。また、モラールダウンにつながる。
社長自身で行うより社労士に委託する方が安心確実、かつ、本業に専念できる。
事業が急成長して「ヒトに関する業務」の仕事量が大変になってきた会社
急速に事業が成長して社員数が増えすぎ、入退社手続きや給与計算業務量が急激に増えかつ複雑になってきた場合。社員が正社員だけでは無くパートやアルバイトを雇用すると労務管理が一気に複雑化します。
さほど難しい作業では無いとは言え、やはり何年かは経験を積まないと自信を持って手続きを行えるというわけにはいかない。かつ、私の経験では知れば知るほど疑問点が出てくるものである。正しく手続きするのは思ったより難しい。特にお金が絡む手続きが多いのでなおさらである。実感として、手続きも頻繁にやらないと忘れてしまうので、従業員数50人ぐらいの会社では数が少ないので手続きを覚えるのに何年もかかってしまうだろう。労災の給付などは生涯を通じて数回しかしない場合もある。覚えろというほうが無理であろう。
こんな時は社労士に委託してしまえば、社員の負担を軽くできる。
特定の時期に「ヒトに関する業務」が集中して困っている会社
月末に集中する給与計算をするために社員にかなり残業代を支払って仕事をさせている場合。繁忙期にあわせて人員を増やしてしまうと、月末や年一回の「労働保険年度更新」や「社会保険算定基礎届」業務の時期以外は、逆に人員が過剰になってしまうのが主な理由である。このような企業は、「労働保険年度更新」や「社会保険算定基礎届」手続きや作業を期日間近になって慌てて行うことが多い。そうなるとかなり大変である。慌ててやってミスが出ないことを祈るばかりある。
社労士に頼んでしまえば確実に手続きを行えるという安心感がある。かつ、人員を雇用したり残業代を支払って行うより安く上がると考えられる。
合理化でヒトに関する業務を外部委託したい会社
合理化による人件費削減で、人事・労務業務の外部委託を検討しているような場合。
社労士に外注すれば、人事・労務の業務をすべて内製化するのに比べると、コストは1/2~1/3程度になると言われている。従業員は営業や生産現場に配置し利益を生まない間接部門はアウトソーシングするのは中小企業でも当たり前の流れになってくるのでは無いか?
社労士にヒトに関するコンサルティングを依頼する
もう一つ、社労士に依頼できる仕事として、人事・労務管理に関するコンサルティング業務がある。
具体的には、就業規則・退職金制度・人事制度(賃金制度・評価制度)助成金・高齢者の賃金設計・就業時間管理・行政官庁調査対応・社会保険料適正化などだ。いわゆる「ブラック企業」と呼ばれないためには第3者の意見を取り入れ慎重に制度設計を行う事が望ましい。どんな社長も自分の会社をブラック企業などとは呼ばれたくないはずだ。また、これから本格的な人手不足時代になってくる。優秀な人材を確保するにはホワイト企業で無ければならない。
- 社労士にコンサルティングを依頼できる業務には次のようなものがある
-
- 就業規則の作成・見直し・変更のコンサルティング(リスク回避型)
- 変形労働時間制・裁量労働制などの導入コンサルティング
- 社会保険事務所・労働基準監督署の調査指導の対応業務
- 助成金の申請代行
- 人事制度全般にかかる賃金制度設計や評価制度の導入コンサルティング
- 退職金制度の設計
- 法律に反しない社会保険料の適正化
- 高齢者の定年後の継続雇用に関する指導
社労士によるコンサルティングのニーズ
社労士にコンサルティングを依頼する場合とは?
社内規則や規定などを整備したい
就業規則や社内規定を整備する理由は企業によってさまざまであるが、そんな社内規則・規定の作成時に社労士に相談し、アドバイスを受けることができる。せっかく作成する就業規則や社内規定を真に有効なものとするにはそれらを運用も含めて熟知している社労士に委託することは有効である。
助成金の申請・受給を考えている
何か返済不要の助成金があれば申請・受給したいと考えているような場合、社労士は豊富な助成金情報を持っている。また、元々助成金は国が企業に制度の整備を促すために作った制度なので、助成金の中には、就業規則の作成や運用実績、各種社内制度の整備が必要な助成金もある。
助成金の申請をきっかけに就業規則の整備を考える企業も多い。就業規則の作成・運用から助成金の申請・受給までの一貫したサポートを社労士から受けられる。
賃金制度を設計したい
賃金制度の一般的な考え方や、自社に合った賃金体系とはどんなものか?といったことも社労士の相談対象になる。
従業員の採用や、モラル向上のために大切な賃金制度については、会社が独自の考え方に基づいて作成していくものだが、基本的な手法や同業他社の水準などをある程度念頭に置いて作らなければ賃金水準が問題となり、人材採用に応募がなかったり、すぐ離職者が出てしまったり、逆に賃金水準を上げすぎて経営を圧迫したりすることがある。
具体的には、「昇給・昇格・賞与の違いは?」「ベースアップと定期昇給とは?」といった基本的な問題から「同業他社の初任給や賃金水準を知りたい」「賃金体系をつくりたい」「能力給や年俸制、また成果給などを導入したい」などの質問や相談に社労士は答えてくれる。
社会保険を整備をしたい
「社会保険に未加入の社員がいる(特にパート・アルバイト)」、「社会保険事務所から調査が入り対応に困っている」、「毎月の社会保険料負担に苦しんでいる」など、社会保険の導入に関して社労士に相談したりサポートを受けることができる。
ベンチャー企業の中には、創業期には社会保険の整備がいい加減である企業も多く、社会保険の整備がそのまま放置されて後々、非常に大きな問題に発展するケースもある。
人的資源管理について相談したい
「優秀な人材を採用したい」、「定年後の高齢者再雇用」、「リストラ」など、人材の採用・人的資源管理に関して、社労士に相談したりサポートを受けることができる。人件費を最小にしながら優秀な人材を採用し成長していくためには採用・配置転換などの人的資源管理について社労士に相談できる。
人事労務関連の最新情報が知りたい
人事労務関連の法改正情報や他社の動向は社内の担当者ではなかなか情報を得るのが難しい。こうした情報を社労士はもたらしてくれるだろう。
社労士に労務トラブルの相談をする
本当に経営者が知りたい内容、労務問題に対して、社会保険労務士に相談したり、意見を求めることができる。社労士に依頼をする本当の理由はここにあると私は考える。
退職関連
-
- やめさせたい社員がいる。
- 早期優遇退職制度を導入したい。
- 成績の悪い社員の給料を下げたい。
- 辞めた社員が、サービス残業分を請求してきました!対応は?
- 有給休暇を買い取り請求された。
- 社長の退職金を用意したい
賃金・労働条件関連
-
- 遅刻とか欠勤の場合の賃金カットについて
- 負担増なのでボーナスは次からやめたい。
- 退職金制度を廃止したい。
- 合法的にもっと残業させたい
- パートの有給休暇について
- パート社員の育児休暇について
労働問題関連
-
- 労働基準監督署の調査対策
- 社会保険事務所から調査対策
- 社内でセクハラが発生しているが、解決する方法は
- 労災が発生後の対応
- 会社の合併を考えていますが、労働条件の隔たりが大きいのですが
- 会社の秘密が漏洩しているようなのですが・・・
人材関連
-
- どうすればいい人材が採用できるの?
- 社員のモチベーションをUPさせる方法
- 社員の離職率が高く、定着しない理由
- 従業員が急に出勤してこなくなった場合の対応
労務顧問の5大メリット
信頼できる相談相手ができる
社長というのは孤独なものです。何かを決断しなければいけないとき、何か情報が欲しいとき誰に相談しますか?長年一緒に仕事をしてきた専務さんでしょうか?それとも奥様でしょうか?それらの人たちは法律に詳しいですか? たとえば、労働時間に関して『うちの会社に残業代はない』では通らないことはご存じでしょうが、正しい計算方法をご存じの社長さんはあまりいません。
労務顧問契約をすれば、何かにつけて気軽に相談できる専門家を確保することができます。様々な相談を重ねていくうちに社内事情もわかってきますから、より的確なアドバイスをすることができます。法律に強い専門家に相談することは、安心して経営をすることにつながります。
手続き簡単!丸ごと依頼
社会保険・労働保険の手続きは意外とたくさんあります。入社・退社はもちろん結婚・出産・育児休業・介護休業など、人に関して何か変化があると必ずと言っていいほど手続きが発生します。しかも、滅多にやらない社長様にとっては、非常に長い時間を費やしてしまうことになります。私たちは、その時間を本業に振り向けていただきたいと考えています。顧問契約をすることによってこれらの煩わしい手続きから解放されます。
法改正情報を確実にお届け
法律というものは毎年毎年何らかの改正が行われています。去年まで適法であったものが今年は違法なんてことが起こらないとは限りません。法改正情報をこまめにチェックし、顧問先に確実にお届けします。同時に対応策もご一緒に考えます。
世の中の相場や情報がわかる
自分の会社や同業者のことはわかっても、世の中の相場や問題に対する対応はほとんど情報は入らないでしょう。専門家同士のネットワークによりたとえば、同じくらいの規模の会社ではどういった制度があり,どのように運用されている。等の情報も手に入れることができます。自社の各種制度を検討する場合に役立ちます。特に、大企業の就業規則を入手してそのまま自社で運用してしまっている場合がたまに見受けられますが、中小企業には中小企業に適した規則の作成方法・運用がありますのでそのようなことはやめた方が賢明です。
監督署などの立ち入り検査に対する対応
どんなにしっかりと会社を運営していても、立ち入り検査は避けられません。問題のある会社ばかりに立ち入り検査をするのではないからです。また、どんな会社でも何らかの問題は発見されるものです。社労士がいれば、あらかじめ指摘されそうな箇所を対策しておくことが可能ですし、万が一指摘があってもも迅速に対応が可能です。
社労士に仕事を頼むときのチェックポイント
社労士に仕事を依頼するときのチェックポイント
社労士に仕事を依頼する場合、どこを見て頼んだらいいのかよくわからないと思います。
ここでは、依頼の際の手助けとなるようにポイントをお教えします。
まず最初に社労士事務所は千差万別だと言うことをご理解ください。
依頼をする側では、ほとんど個々の事務所に関する情報が入りませんので、「どこの事務所でも同じだろう、だったら安い方がいいなあ。」という考えに陥りがちです。確かに価格は一つの重要な選択肢であることは間違いありません。しかし、ちょっと待ってください。社労士界には(というか士業の世界には)統一した教育カリキュラムはありません。あるのは、国家試験だけです。国家試験は法律知識を問うだけで、業務を行う上でのマナーやスキルはおのおのが過去の経歴の中で身につけたものです。
従って、すべての事務所が全くちがうと考えた方が間違いありません。
具体的なトラブル例
①相談時のトラブル
電話相談:対面相談→言葉使いが悪い。上から目線で話された。態度が悪い。
メール相談→返事が遅い。かえってこない。
②見積もり・契約時のトラブル
明らかに契約を急がされた。
業務範囲が曖昧で不安だった。
③手続き時のトラブル(業務実施上のトラブル)
とにかく連絡がなくどこまで進んでいるのか不安だった。
結果的に期日に遅れた。
④請求時のトラブル
費用が高い。
オプションで不明瞭な追加請求が含まれていた。
⑤その他
手続き後のアフターフォローがない。
質問しても時間がかかる。
契約内容と実際が違う。
チェックポイント
このようなことがないように次のことをチェックしましょう。
1.お問い合わせの時
態度や言葉遣いをチェックしましょう。
横柄なのは困りますが、あまり自信がなさげなのも問題かもしれません。
併せて経験年数なども聞いてみましょう。
2.見積もりから契約にかけて
依頼した内容が見積もりにきちんと入っているか?
余分な内容がないか?しっかりと聞きましょう。
「何でもお任せください。」は結構危険です。
契約を急がせる先生は仕事が薄いのかもしれません。
ここで一言、「相見積もり」はかまわないと思いますが、先生によっては嫌う場合もあります。
だいたいの場合は、皆さんも事業主さんなので経験があると思います。マナーは守って「相見積もり」をしてください。
3.費用の支払時期等も事前に確認しておきましょう。
4.アフターフォローについても確認しておきましょう。
専門外のことも相談に乗ってくれるか?など。
さいごに「まとめ」
士業事務所は人と人との信頼関係で仕事が成り立っています。末永く良好な関係で仕事をさせていただけるようにお願いします。
良い社会保険労務士を探してみる
良い社会保険労務士とはどんな労務士でしょうか
あなたにとって良い社会保険労務士とはどんな先生でしょうか?何でも言うことを聞いてくれる先生でしょうか?それとも時には耳の痛いこともずばり言ってくれる先生でしょうか?聞きたいことがあるときには電話で問い合わせをするとその場ですぐ答えてくれる先生でしょうか?それとも後日、きちんとまとめた書類を持参して説明してくれる先生でしょうか?どのような先生がいいか悩んでしまいますよね。ここでは、タイプ別社労士の特徴を一緒に考えてみたいと思います。
若い社会保険労務士の特長
どのくらいの年齢を若いというのか?疑問に思う方もいあると思います。現在、社労士試験の合格者は20代30%、30代40%、40代20%、50才以上10%という感じです。合格者だけで見ると中心はすでに20代30代に移っています。これは、社労士試験が暗記中心であると言うことと無縁では無いと思います。開業される方も確かに若い方が増えている感じがします。これらの先生の特徴として、若いけれども経験が豊富であると言うことを打ち出しておられます。私の印象として、
- 法律知識が豊富
- フットワークが軽い
- 人生経験がないため臨機応変さに欠ける
- とにかくまじめである
といったところでしょうか。一方で「ベテランの先生」になれば
ベテランの先生の特徴
- とにかく多少のことには動じない安心感
- その反面強引なところもある
- 自分のやり方があり、割と頑固である。
- 新しいものには対応しづらい面もある。
そして、もう一つの巨大勢力である女性社労士。
女性社労士の特長
女性の方が多数活躍されているのもこの業界の特徴です。時間に自由がきくせいでしょうか。私が所属されている支部にも支部活動に積極的に参加されている方が何名もいて、あまり熱心でない私は大変ありがたくお世話になっています。やはり女性ならではの特長を生かしてご活躍の方が多いのかなあ〜と思います。
- 年金を中心にやっている方の割合がかなり多い印象。
- 女性ならではのきめ細やかなアドバイス。特に女性経営者にはいいのかなあ?と思います。
- 女性を顧客にする業界にはいいと思います。(美容院、ネイルサロン、幼稚園・・・)
- 厳しい労務問題に対処できるか、少し疑問が残ります。まあ、男性でも一緒ですが・・
結局の所良い社労士とは、そして良い社労士と出会うには?
私の考える良い社労士とは、依頼人の目標とすることを達成するための手助けになる社労士です。「何でも聞けるおつきあいがしたい社長さん」もいれば、「会社の中のことにはあまり口だしされたくないから手続きだけを安くやってくれればいい」と考える方もいます。「就業規則などを整えて、働きやすい職場を作っていこう」や「法律の解説だけでなく、その運用のノウハウがほしい」という方もいます。これらは全部、私が関わってきた方々の一例です。「どうして選んでくださったのか?」をお聞きすると、ネットで見てあらかた決めていたという方もまれにいますが、ほとんどの方は「実際にあってから決めた」かたです。その決め手は千差万別です。そう考えても、
その先生を知るきっかけは紹介であっても、ネットであっても実際にあって話してみることが肝心といえるでしょう。
社労士と会う前に何をしておくか
社労士を探し始める方は何らかのきっかけがありますよね。会社を経営していても何も無ければ専門家に相談しようなどとは誰も考えませんし、すべての社長さんが社会保険労務士という職業が存在することを知っているわけでもありません。まあ、私はそんなにうぬぼれてはいませんから認知度は50%以下だと思っています。余談ですが、社会保険労務士は年金のヒトだと思っている方も多数います。(例の消えた年金問題のせいですね。)
「手続きを頼みたい」とか「就業規則を作りたい」や「ただで情報だけ聞きたい」などいろいろあると思いますが、せっかくですから「ご自分の会社をどうしたいのか」と言うことを考えてみてから相談に行くことをおすすめします。その方が、社労士も気分が乗ってくると思いますし有意義な話が聞けると思います。
社会保険労務士の仕事
社会保険労務士の仕事は2つに大別できる
社会保険労務士の資格は企業の経営者があいての労務管理と個人が相手の年金相談に大別できます。ここでは労務相談について考えてみたいと思います。
1号業務・2号業務・3号業務
1号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出代行」業務を言います。
(例:健康保険、雇用保険、労災保険等への加入、脱退、給付手続き/助成金等)
2号業務とは「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成」
(例:労働者名簿・賃金台帳の作成/就業規則、各種労使協定の作成等)
3号業務とは「人事や労務に関するコンサルティング」
(例:労務管理、賃金管理、社内教育などのコンサルティング等)
を言います。
これらは社会保険労務士法第2条に規定されています。1号とか2号というのは「第2条第1号」・・・ということです。
社会保険労務士の独占業務と他士業による法律違反
この中で、1号業務と2号業務は、社会保険労務士にのみ許された独占業務になっています。他の方は業としてこれを行うことはできません。時々、税理士さんが届け出をしてしまったり、行政書士さんが就業規則を作成したりしていますが、明確に法律違反だといえます。彼らにすれば、業として行っていない。と主張するつもりなのでしょう。しかし、詭弁であることは明白です。ご注意いただきたいのは彼らに仕事を発注すると事業主様も罪に問われることがあると言うことです。
3号業務は、社会保険労務士の資格を持ってなくても行うことができます。
しかし、税金に関することを私に依頼する事業主がいないように、人事・労務のプロである社会保険労務士に依頼するのが、当然と思われます。もし、労務コンサルができるという他士業がいたとしたら、ご自分の本業がきちんとできるのか怪しまれます。どの先生業にしろ自分の領域を大事にすれば他士業の領域に首を突っ込むヒマなどないはずですから。
具体的にはこんな仕事です。
例えば、会社で新しく従業員を雇った場合、「雇用保険資格取得届」・「健康保険・厚生年金保険資格取得届」その方に家族がいれば「被扶養者関係の届け」を行います。逆に、退職者が出た場合、「雇用保険資格喪失届」「健康保険・厚生年金保険資格喪失届」を提出します。
「●○届」の提出は1号業務、さらに提出時に必要になる賃金台帳や出勤簿等の調整は2号業務となり、社会保険労務士のみが出来ることとなります。
3号業務としては「労働時間管理」・「問題社員への対応」・「定年制度、再雇用制度の見直し」・「育児・介護休業制度の取り扱い」・「ハラスメント対応」・「メンタルヘルス対応」などあらゆる問題を解決するのが社会保険労務士の仕事になります。近年の労働環境の変化により社会保険労務士の扱うこれらの問題は非常に多岐にわたっており、かつ、複雑化しています。また、一つ対応を誤るとその解決には非常に多くのエネルギーを費やすことになってしまいます。